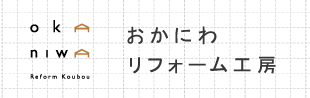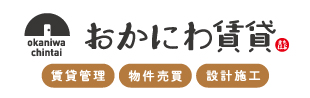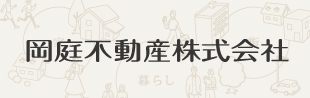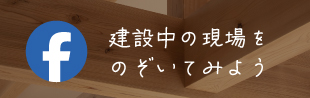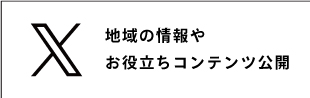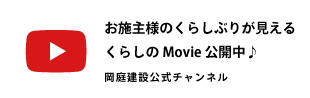IKEDA隊長コラムCOLUMN
最新記事一覧

竣工写真は家族みんなで
おかにわで注文の家造りを進めると竣工写真の撮影を行います。家族みんなで竣工写真。そして「フォトアルバム」を作成します。(*専属のプロカメラマンが、家と住み手様と一緒に撮影します。) そして、完成記念としてお施主様にもお配りするのと、これから家造りを始める方々にもご覧いただきながら打合せなども進めて行きます。 もう100冊以上はそろっていますので、過去に手掛けた家づくりや工夫の数々が改めて見ることができます。そして、それぞれの想いとともにハウスネーミングもよく考えて来たものだと、たまには自分を褒める隊長でしたー・・・笑。丁度幾つかの、アルバムが完成してきましたので、一部をご紹介しますね。 先日竣工しました、日野市の「とおりみちの家」北側の借景を活かした建物配置やプランそして窓。キッチンや、小上りタタミからもそれらの景色が望める、この立地と住まいてならではの家が完成しました。当初は茶系のガルバリウム鋼板の外壁予定でしたが、打合せを重ねダークブルーに。でも青空と北側の借景、そして木とのコントラストがお似合いですね。。お引き渡しの関係で、見学会で設営した家具類を撤去しなければならず、少し寂しい気はしますが、空間の変化や、キッチン奥に見える借景の木々がハッキリ見えてかえって何も無い方が「とおりみちの家」そのものが伝えられる気がします。小上りのタタミその向こうにあるワークスペース。障子を開けると玄関と繋がり、通風や行き来する家族の気配を感じる事ができます。左奥の階段も、大工の技術で家具的に制作。木を活かして造作し、デザインだけでなく、一部を収納にするなど機能的な要素も取り入れ、かつ、北庭の景色が、階段の昇り降りする際に目につく窓配置とも絡めています。この借景が四季を通して「とおりみちの家」の暮らしをより豊かにしてくれますね。 そして、手を振る住い手様。一枚のご紹介ですが、内外部を併せ、モデルの様に幾つか、家族の記念写真も撮影させて頂いています。OBの住み手様からもよく、月日が経って改めてみると家づくりした時が懐かしく思えると共に、経年変化による佇まいがよりよく見えるー。そう、自らが実現した住いは家族と共に成長していくものです。このフォトアルバムはそのことも思い出させてくれるようです。 *SNSインスタグラムでも住みて様の暮らし振りを覗く事ができます! 隊長
2017.03.30(木)

地域貢献〜庭之市〜
3月25日(土)に開催された「庭之市〜おにわのまるしぇVOL7」。(西東京市) 今年も地域貢献、地域活性化に繋がるイベントを開催させて頂きました。 庭之市は、単にお祭りやイベントと言うものではなく、地域には大きくは無いけれど、魅力あるお店が沢山あるのだということを知って頂く、そして、地元のお店でお買い物等をすることで、地域にお金が循環する。そのような事を地域に住まう人たちが少しでも気がついて頂ければ、より楽しい街にツナガルのではと取組み早5年目を迎えます。 そして、この度も大勢の方々が足を運ばれました。詳しくは後日HPで「庭之市開催報告」をご覧頂ければと思いますが、ダイジェスト的にに隊長から速報でお伝えしておきますね。 まず、毎年会場となる、旧モデルハウス、3軒の住い手様宅、そしておかにわリフォーム工房と、岡庭不動産の社屋兼賃貸住宅の建物の間にある駐車場を利用して開催しています。 今年は、こちらの駐車場を第一会場、徒歩10分程度の距離にあるモデルハウス「RーECO HOUSE」会場を第二会場として開催されました。晴天のポカポカ陽気の中で大勢の人がご来場に。 3日前の天気予報では雨予報・・・・・汗。一時は延期も視野に天気に注目しておりましたが、なんと2日前には時々晴れ・・そして前日には「晴!」の予報に!。気温も低いとの予報でしたが、主催者、出展者の祈りが届いたのかもしれませんね。 お陰様で、ポカポカ陽気故、クラフトビールなどのコールド商品も売れていましたねー。そして、出展者、参加者含め沢山の笑顔を見ることができました。 初登場、クラフトビールの「ヤギサワバル」さん。終了時には完売となる勢い!地元西東京市で、クラフトビールが飲めるのは嬉しいですね!ってこのようなお店があることを是非知っていただきたいです。(上写真)続いて、レギュラー出演の、地元西東京市のキャラクター「いこいーな」毎度、子供達に大人気ですね。*庭之市は市の公認も頂いています。(上写真) こちらも初出展「ヤギサワベース」駄菓子販売や射的など子供達で行列でした。(上写真左) こちらはワゴンカーとして初出展「88オッタントットダイナー」さん。(移動販売)ローストビーフ丼やドリアなどが150食近くも販売され売れ切れに・・隊長も頂きましたがとても美味しいです。多摩エリアを拠点に普段は、大手町近辺で販売しているそうです。(写真上)そして、岡庭建設で家造りされた住い手様、農園おかにわファームを手がける主力メンバーで出店です。その名も「おかにわキッチン」!今回で3回目の出店で、ファーム餃子という、野菜を活かした餃子を販売しています。味付けが絶妙で、ビルーにピッタリ・・笑 こちらも初出展「eggg(エグー)」さん。良質なたまごで、半熟卵入りカレーパンや、プリン等を販売されていましたが、開始早々行列ができ、こちらも終了までに完売となりました。という事で、品物がないなかで記念写真です・・・笑。(写真上) そして、恒例のおかにわ建設の大工や、監督などによる「MY箸づくり」こちらも、お子様に大盛況のようでした。ものづくりが面白いと!将来、大工さんなどの職人を目指してもらえれば嬉しいですね。(写真上) こちらは、第二会場となるモデルハウス「RーECO HOUSE」 第一回から人気の家具出店「レイクサイドファクトリー」さんそして、庭之市VOL7での目玉でもある「BYO-BU/屏風」「小上りタタミキット」など、家の中に居場所をつくる家具を展示販売させていただきました。おっと、その前に目玉商品の小上りタタミキット上で・・・・ そう、西東京市近辺で大人気の落語家「天家 燈四郎(あまや とうしろう)」氏による落語寄席が計2回開催され、満員御礼大好評でしたー。ちなみに、天家 燈四郎さんも、住まいてでもある、おかにわファミリーなんです。「ひばりいこい亭」というネーミングのお宅にお住まいです。施工例→「ひばりいこい亭」 で、こちらが「BYO-BU/屏風」という新商品。建具を組み合わせる事で、屏風になりその折りたたみ方や、パネルの構成により、書斎などの居場所になるのです。家の中の居場所(木箱イン木箱と呼んでますが)として、新築住宅だけでなく、既存住宅や賃貸住宅などにも置くことができます。詳しくは発表ページを御覧くださいね。お子様用も販売されていますからー。 という事で、駆け足でお伝えいたしましたが、「庭之市VOL7」も大盛況で終えることができました。微力ではありますが、地域の一企業として地域貢献、地域の活性化に繋がれば幸いです。以上ダイジェスト報告でしたー。 ご来場された皆様ありがとうございました!! また、来年「2018年 庭之市 VOL8」でお会いしましょう!! 隊長
2017.03.26(日)

屏風/BYO-BU 発表します【庭之市にて】
25日に開催される「地域活性化イベント・庭之市」 そこで新たな暮らしの提案「BYO−BU/屏風」・「小上りタタミキット」を発表します。 【小さな空間には機能を 大きな空間には景色を】 地域の20代建具職人+デザイナー*おかにわ建設のコラボで生まれた新たな暮らし方の提案です。 屏風を組み合わせ、小さな部屋やワークスペースに、仕切りにしたり飾り付けたりと、屏風から新たな 暮らしの世界を会場にてご覧頂ければ幸いです。 当日は実物の展示、並びにパンフレットを配布致します。 詳細は「SOF]のページを御覧くださいね。 その他、庭之市会場では多数のお店の出店やワークショップなどが開催されます。お楽しみに!! 隊長 ◯庭之市公式HPへ◯おかにわ建設庭之市のお知らせ
2017.03.24(金)

住まい手様のためにも
今週時はじめに突然の訃報が・・・ 2年前、丁度今と同じ季節頃に西東京市に完成した 住い手様(ご主人様)が先週末に亡くなられました。享年42歳。あまりにも早すぎます。 先日スタッフともども最後のお別れをして参りました。 今だからお伝え出来るのかもしれませんが、難病におかされていることを設計中に知りました。 しっかりした材料で、安心安全な家と長期優良住宅で建設する。家が完成した後も、しっかり面倒を みてくれる会社にと、一生懸命に家造り学校や見学会に足をお運びになられ、材料のこと、性能 のことだけでなく、会社の取組のことなどを一つ一つ確認しながら検討されていました。 その当時、最愛のご家族様が安心して暮らしていけるために、長きに渡り任せられる会社にと一生 懸命だった姿が、今思い出されとても胸が痛みます。 その想いが形になり、木の温もりある空間、お子様たちが元気で、そして家族が楽しく暮 らしていけるためにと、のぼり棒の他ご主人様をはじめ、ご家族皆様の拘りや工夫が数多 く施された住いが完成しました。 2年弱の月日、住いの中には楽しく過ごされたご家族の思い出が沢山詰め込まれています。 私共も選ばれた地域工務店として ご主人様の想いを引き継ぎ、ご家族の思い出一杯の住まいを守り続けて参ります。 ======================================== ご主人様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。 隊長
2017.03.22(水)

東久留米/きのえみちの家
東久留米市にて竣工した「きのえみちの家」3連休の2日間を利用して完成見学会が開催されました。天候もよく、日中は、ぽかぽか陽気でしたね。 「きのえみちの家」は延べ20坪の家決して大きな家ではありませんが、規模を感じさせない工夫が至る所に施されています。 【きのえみちの家って?】「きのえみちの家」は道を挟み母屋が位置していることや、母屋の木々との応答や木の家などを含め名付けたハウスネーミング。下の写真は、その母屋の木々の谷間から見える風景。【豊かなリビング空間と居場所】リビング空間にちょっとした出窓?出窓にして物おいたりしたい!と思われる方も多いことと思いますが、「きのえみちの家」の出窓はちょっとした居場所として利用しています。そう、腰掛けて本を読んだり、そこからテレビを見たり、家族と会話したりと出窓の新たな利用方法でもあります。【おしゃれな家具も】テレビ台や、ワークスペースなどの家具も制作させていただきました。若き設計担当の持田隊員と同世代のお施主様の感性から生まれた素敵なデザインです!。足となる黒のスチールがアクセントです。【生活空間も】大事な生活空間も豊かに。母屋の木々等の景色を「きのえみちの家」に取り込むために、家のコーナーとなる位置に全開口型の窓を設けています。この全開口になることで、木々を眺めるとともに、一体となるデッキテラスが床と繋がり、より広さ感を生み出してくれます。このような一つ一つの積み重ねが家の規模以上の豊かな暮らしにつながっていくのです。【完成見学会にお施主様も】完成見学会では私達だけでなく、お施主様もなんと参加!自らの家造りのエピソードやプロセス、そして「きのえみちの家」の工夫や魅力をご自身から、これから家造りをご検討の皆様にご説明頂きました。お施主様参加効果か・・笑。お陰様で、大変多くの方々にご来場頂くことが出来ました。 規模以上に広く感じる!。土地探し、家は規模から考えては駄目ですね・・・。 などなど様々な感想をいただきました。 ぜひ、「きのえみちの家」をご覧になられた事から、皆様の家造りに活かされれば幸いです。! 隊長
2017.03.20(月)

省エネ住宅/既存住宅
今週は、国策系の委員会や団体の会議の多い週でした・・汗 2020年の住宅の省エネ住宅適合義務化に向けて,様々な政策や制度がはじまっています。この4月からは、大規模建築物については義務化がスタート。いわゆる、国が定める省エネ基準の適合がなければ工事も始められなくなると言うことですね。世界的な低炭素化社会に向け、国内における建築部門でもこのような制度が急ピッチで進められています。 その中で住宅の省エネ性能を高める設計や施工の基準や手法などを義務化される前にしっかり国内の技術者に学んでもらうために、5年前からテキスト作成のもと全国的に講習会も開催されています。隊長もそのテキストづくりに携わっております。 先日は次年度の講習会テキストの検討を進めるべく委員会でもありました。 →講習会は「住宅省エネ技術講習会」へ翌日・・現在全国3000社の工務店団体「JBN・全国工務店協会」の理事と政策調査部会の部会長を努めており、国土交通省の他、政策的な制度説明を受けたり、意見交換を手がけたりしております。 全国17エリアのメンバーと共に日々、地域の住生活をより良いものにしていくべく、各エリアからの声も行政に届けさせていただいております。 近年は、省エネに関係すること、そして、既存住宅(中古住宅)の活用方法等の政策が急務に進められております。 優良な既存住宅の登録制度も間もなく法律化かれる?→「安心R住宅制度」 専門技術者でも、情報の把握理解するのに大変な部分もありますからこのような事を噛み砕き、地域の消費者の方々にいち早く情報をお届けできるよう対応して参ります! 隊長
2017.03.16(木)

木箱の家/ひとつめの家完成
3月11〜12日まで西東京市で開催された「木箱ガルテン2期&ひとつめの家完成見学会」地元西東京市で2軒同時の完成見学会となりました。(第二期は二棟の工事が進んでいます) 「木箱ガルテンⅡ」の近所では梅の花が咲き始めてきました。でも、日中は穏やかな気候ですが、朝夕はまだまだ冷え込む季節ですね。完成したのは右側のおうち。(左側のお宅は5月ころの公開予定です。) 【木箱ガルテンとは?】改めてになりますが、2010年ー2011年グッドデザイン賞を受賞したおかにわのつくる「木箱の家」共感いただいた農家さまの想いから始まった社会的な取り組みです。「ガルテン」とは農園などを意味し、この街には体験農園(おかにわファーム)が併設されています。 コンセプトは「人」・「食」・「住」 そして今後さらに求められる「自給自足できる暮らし」木箱ガルテンの街の家々には、太陽熱を暖房エネルギーや給湯エネルギーとして利用していきます。 2011年、地域工務店と農家さまとのコラボレーション「木箱ガルテン」が誕生し早5年半・・・。この新しい取り組みに共感してくださった多くのユーザーさまの声にお応えし私たちは自然災害に強い家のあり方を「木箱ガルテン」を通して伝えていくこととなりました。 この2,3月頃は朝夕の気温が下がりますが、太陽高度は高くなり日射熱は強くなります。そう、太陽熱利用をしている、木箱ガルテンは日中の太陽熱を家に送り込み暖房エネルギーとして活用していますので、室温も自然熱でどんどん上げてくれます。本日も22度に・・。正しく太陽熱の恩恵ですね。エネルギー源は無料ですし・・・笑。 さて、そのようなガルテンⅡですが、木を多用した空間に参加者様からも好評頂きました。という事で、たまには空間の写真だけでなく、部位的なところをお伝えしましょう。 下の写真は、宙に浮く和室・・笑。と言いますか、リビングの延長にある、小上りよりも低い、セミ小上りとでも言いましょうか、リビングから少し上がる事で空間のメリハリを生みます。丁度、ご見学のお子様達もくつろいでいますねー。 このセミ小上りには部分的に無垢材を張り、時にはダイニングテーブル等を置いたりでき暮らしの変化を愉しめるスペースでもあるんです。 下の写真は、階段横にあるプチ洗面。2階に洗面やお風呂がある関係で、1階には帰宅後に手洗いが出来る空間を設けています。また、木でつくった階段の横からのプチ収納。空間の利用方法に比較的皆さん目を惹かれていましたねー。 上は2階にある洗面室。木のカウンターの上に、いわゆる学校の理科室で使うよう実験用のシンクを洗面に利用。シンクを深くすることで、靴が洗えたりするなど、多目的に利用することが可能です。利用方法に併せて水栓などもチョイスしています。 工夫一杯のガルテンⅡとひとつめの家。大変多くの参加者皆様にご堪能頂く事ができました。合計8棟が連なる街が間もなく完成です。月日がその街の風合いを更に深めてくれると同時に、人の輪や絆がより良い地域を育んでくれることでしょう。 次週は、隣町、東久留米市にて「きのえみちの家 完成見学会」が開催されます。「決して大きな家ではないけれど、その中には大きな暮らしが詰め込まれています」 次週はお施主様自らがスタッフとして、お住いについて語ってくれます!中々、このような機会はありませんから是非住まいて様から様々なご意見を聞いてみてはいかがでしょう! 次週もお楽しみに!!東久留米にいこう!! 隊長
2017.03.12(日)

既存住宅の活用/東京都
昨日は第3回 東京都既存住宅流通活性化方策検討会に委員として出席です。 28年度で計3回に渡り既存住宅流通(=中古住宅流通)に関して都民が安心安全に購入していく為のスキーム等に関し地域住宅を手がける工務店を代表し出席してまいりました。委員会会場は都庁です。その上で、東京都のより良い住宅や住生活に向けての住宅政策が掲げられています。 ①良質な家づくりの推進②既存住宅を安心して売買等ができる市場の整備③消費者や住宅所有者に対する普及啓発 これから都内でも加速化していく、少子高齢化社会、人口、世帯減少からの空家問題等。その上で、既存住宅の利活用は急務です。また昨今、既存住宅=中古住宅を購入してリノベするなどのニーズや安心安全な売買取引による円滑な流通性なども求められます。 既存住宅は、新築住宅と違って、誰がどのように利用してきたか未知数です。そのことを判別していくためには、住宅の診断=インスペクション、価値評価=不動産・金融など工務店や宅建業者の技量、采配がとても重要です。しかし、まだまだ、この様なノウハウを持ち併せた方が少ないのが現状です。岡庭建設、隊長もまだまだ学ぶ必要性もありますが、長きに渡り、建築と不動産をワンストップで手がけて来たこともあり、近年このような場で経験を元に意見を述べる役割も多くなっています。(適正かは_・・ですが・・笑) 委員会の内容等につきましては、都度、東京都のHPで掲載されて参りますので、ご興味のある方は、都のHPを御覧くださいね。(第三回の内容は後日公開されます) 第1回 東京都既存住宅流通活性化方策検討会 (平成28年11月2日)における資料及び議事概要 第2回 東京都既存住宅流通活性化方策検討会 (平成29年1月27日)における資料及び議事概要 微力ではありましたが、28年度都の住宅政策へ寄与させて頂きました。m(_ _)mまた、より良い住生活に繋がれば幸いです。 隊長
2017.03.09(木)

家づくり学校1時間目/3月〜家造りを学ぶ〜
イベント報告が逆になりましたが、一昨日に行われた「家造り学校1時間目」の模様です。 家づくり学校1時間目は、これから家造り始める方の基本講習会でもあります。 家造りを始めるうえで何からはじめたら良いのだろう。 家造りの本をたくさん読む?・・・・読み過ぎもかえって逆効果なんですね。 展示場を見に行く?・・見に行くことは否定しませんが、ある心構えで行かないと大変な事に。。 じゃーどのようにすればよいのか・・・ という事で、家造りについて誰が教えてくれるのか・・ 其のような声に応え、今から10年前にこの家造り学校が始まりました。 延べ900人以上の方が参加されてきています。 おかにわの「家づくり学校」は西東京市の逸品事業にも認定されているサービス。 社会的なサービスでもあるのです。今回も、土地探しからはじまる方から、既に土地をお持ちの方まで様々な立場での方々が参加されました。 参加されたアンケートからも ・いろいろな経緯を踏まえて今回参加することに成りましたが、住宅の奥深さをしれました。・今まで予算がー番と思っていたので、参加して新しい目線でとても新鮮でした。・家造りについての基本的な考え方が学べた。まだまだ基礎的な部分をも学びたい!・どのように生活したいか。ということを中心に家造りを考えると言うコンセプトがいい。・「家をつくるのではない」という大切な考え方をすることができました。等々 多くの感想をいただきました。 家づくり学校は、様々な世代の方々が参加されます。特に、一時所得者でもある、子育て世代の方々も参加されます。おかにわ保育園?ではありませんが、セミナー中、お子様もテレビを見たりおもちゃで遊んだりと、熱心に学ばれるご両親様をサポート中です・・・笑。 次回は4月 8日(日)に家づくり学校1時間目〜家造りのススメ方〜 4月15日(日)に家づくり学校2時間目〜しっかり作る家性能編〜 が開催されます。間もなくHPで募集開始いたします。 隊長
2017.03.06(月)

住み手の家を見学/半平屋の家
【2016年にウッドデザイ賞受賞「みはらしだいの家〜半平屋の暮らし〜」】 本日はその受賞を記念して、バス見学会が開催されました。 住い手様の家ですから、バス1台限定(30名様満員御礼)とさせて頂きました。m(_ _)m。*キャンセル待ちの方々にはご迷惑をお掛け致しましたが、ぜひ次回にご参加頂ければ幸いです。 さー、バスを降車して、住宅街ともあり、現地まで徒歩で向かいます。現地到着後は、まずは隊長から、「みはらしだいの家」の概要を説明させて頂き、続いて今回の見学に多大なご協力頂きました、お施主様をご紹介、参加者皆様とご対面・・笑!。 長きに渡りこの街に住み、街並みと街の景色の再現をと、ひときわ低くと半平屋の家に。そして、家の大きさ以上に大きな暮らしを楽しむエピソードなども・・。【半平屋にみはらしだい】いざ、楽しみにしていた、半平屋の空間へその前に、玄関の上にあるものは・・・まさしく、家のタイトル通りの「みはらしだい」が・・・この「みはらしだい」は、コンセプト通り、自らの街を眺めたり、夜空を眺めたり、洗濯ものを干したりと多様な使い方のできるスペースでもあり居場所でもあるんです。 【外壁がオレンジ色?】オレンジがかった外壁は、焼杉といって、スギの板を焼いて炭化させたもの。塗装もされていますが、炭化作用で雨はじきもよくたりするなどの他、防虫防腐効果を高め、素材の寿命を少しでも長くします。【半平屋の空間には楽しさが一杯】半平屋とは、平屋と2階建ての中間的な建築手法。弊社の家造りで多用しています。1階の天井程からはじまる屋根の勾配を利用して一部を2階空間に。 故に、1階の天井も高くなり、空間的な広がりを感じることができますし、其の吹き抜け的空間から、家族の気配や繋がりを生むことができます。 【風を抜く窓】↓写真左上にある窓は、365日、日が差し込むことのない窓。そう、通風のためにある窓なんですね。軒の長さが1.5Mもあることから、このマドは通風専用窓ということになり1階だけでなく、2階の部屋にも風を注ぎ込むことができるんですね。 【あしぶらりん・・】↓写真中央に座るお子様たち。そう、書斎のスペースになるのですが、時には吹き抜け側に足をぶらりんと伸ばし、ぼーっとする居場所?・・と具体的な目的があるわけではありませんが、なんか足が伸ばせて、自分の家が眺められた面白いな−と、お施主様の発想を含めこのような居場所が生まれる事になりました。皆さん、この居場所も堪能されてましたねー。【天井はたかくないけれど】天井は高いほうがいいと思っていたけれど・・・なんだか適度に低いのもいいねー。と多くの方々がお話しているのが聞こえました。その通りで天井は高いほうが良いのではなく空間のメリハリが大事なんですね。でも、日本人って意外と、低い、狭い空間が好きなDNAをもっていて、体感すると意外と悪くないと言うことに気がつくものなのですね。まーこれも空間設計の極意といいますか、そのバランス設計が大事なんですね。【杉の木がいっぱい・太陽熱もいっぱい】「みはらしだいの家」は構造材も杉ですが、床、壁、天井にも杉材を多用し、木のぬくもりを感じる空間に、そして空気集熱式ソーラーで太陽熱をふんだんに取り込みます。 杉材は材の中に空隙が多く、素材そのものが柔らかいという短所がありますが、足ざわりなどが良かったり、熱を蓄えるなどの冬の季節でありながらも床の冷たさを軽減したり、直射光や日射や熱エネルギーを素材そのものに蓄熱できる長所があるんですね。 という事で、「みはらしだいの家」の後は、「木ノベーションスタジオひばりヶ丘」や「RーECO HOUSE」など弊社のモデルハウスなどもその後ご見学頂きました。 参加された皆様、住まい手の家を見学されていかがでしたでしょうか。完成した建物だけではなく、実際に住まれている家や暮らし、そして、住まい手様から生の声が聞けて、さらに家造りの楽しさや、不安を解消できたのではないでしょうか。ぜひ、今後の家造りに活かしてくださいね。また、今回キャンセル待ち他ご参加できなかった皆様も次回にご参加頂ければ幸いです。! そして、何よりも今回の見学会の多大なご協力を頂いた「みはらしだいの家」のお施主様に改めて感謝申し上げます。m(_ _)m えー上の写真はバスガイドも努めさせて頂きました隊長です・・笑。 隊長
2017.03.05(日)
タグ一覧
- 岡庭建設
- おかにわ賃貸
- おかにわ建設東伏見
- NENRIN(年輪)Original Blend Coffee
- トリプレッド
- コーヒー
- HEAT20
- G2やG3
- 「G2-B」や「G3-A」
- 省エネ住宅
- 断熱性能等級
- 夏期日射取得
- 冷房削減
- 住まい手忘年会
- おかにわファミリー
- BCP(事業継続計画)
- 全木協
- 木造応急仮設住宅
- 避難訓練
- みらいエコ住宅2026事業
- GX志向型住宅
- 長期優良住宅
- ZEH水準住宅
- 既存住宅の省エネリフォーム
- YKKAP
- 住宅医スクール
- 性能向上リノベの会
- 用途地域見直し
- 準防火地域
- 最低敷地面積
- 社員大工
- 大工
- 建設キャリアアップ(CCUS)
- CCUS
- 西東京市
- 地域
- 隊長の活動
- 戸建て賃貸
- GXZEH
- GXZEH-M
- 省エネ新水準・新定義
- 不適合建築・違反建築・検査済証なし
- 木造4階建てアパート
- 性能向上リノベ
- IKEDA隊長チャンネル
- 設計技術
- 建物探訪
- リフォーム・リノベーション
- 現地調査
- 地鎮祭
- 外部イベント
- 情報
- 社内
- まち探訪・建物探訪
- メディア関連
- 西東京市エコプラザセミナー
- 表彰・受賞
- ゼロエミガルテン
- 講演・講師
- 見学会
- 新築
- 隊長ニュース
- リノベ
- 分譲
- 性能